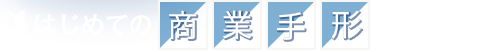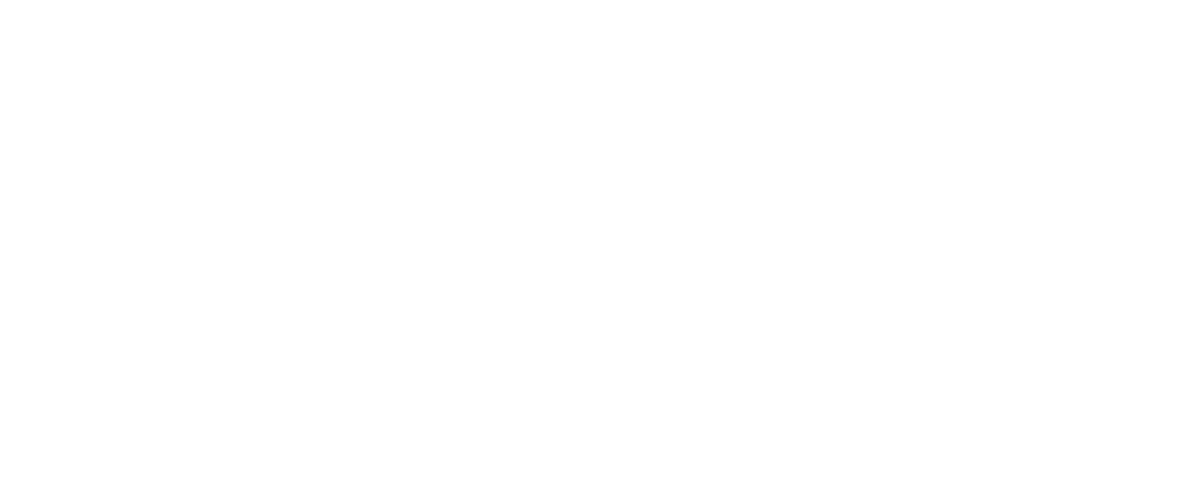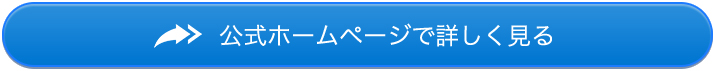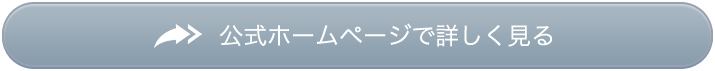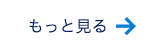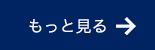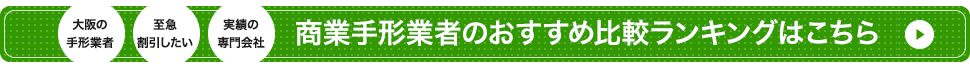手形割引の支払利息の計算方法
手形には期日より前に現金として受け取る場合には手形割引として、期日前に受領するものが手数料を支払うことになります。
その手形割引で生じた手数料を支払利息として捉えて計算をするようになりますが、それはどのような仕組みとなっているのかを認識しておくことが必要になります。
支払利息というのは手形割引の金利と言われるもので、別の呼び方で割引率とも言われて、その金利によって手形の払戻しの手数料が大きく左右されます。
元々の額面が大きな金額の場合、この金利が1%や0.5%でも変われば、手形割引をした時の手数料が大きく変わってくることになります。
例えば、1,000万円の額面の手形で同じ支払期日の日数であり、金利が1%違うとした場合になりますが、次のように支払利息が変わってきます。
【金利が8%ので支払期日まで30日の場合】
A 10,000,000 ? 8% ? 30/365 = 65,753円
【金利が7%ので支払期日まで30日の場合】
B 10,000,000 ? 7% ? 30/365 = 57,534円
AとBとの支払利息の差額で8,219円も金額に開きが生じてきますので、金利というものは1%でも違うと大きく金額に影響するのです。
手形割引の支払利息を有利にするのは金利
では、手形割引の支払利息というものは金利と支払期日までの残日数を掛けあわせて決まるものになりますので、金利は低ければ尚良いものとされます。
今では銀行で定期預金を預けても0.05%や大きな金額や様々な優遇の策を使っても0.5%もあるかという金融機関ばかりですので、手形割引においても1%でなくても0.5%も変われば、それだけ銀行の定期預金で受け取る利息なんてものはすぐに回収出来ると言うことです。
従って、金利というものはこちらが受け取る利息は高ければ高いほど良くて、こちらが支払う利息は低ければ低いほど良いという原理はしっかりと覚えておきながら、少しでも手形割引は支払利息を少なく済ませるように計算することが大事です。