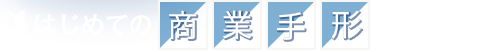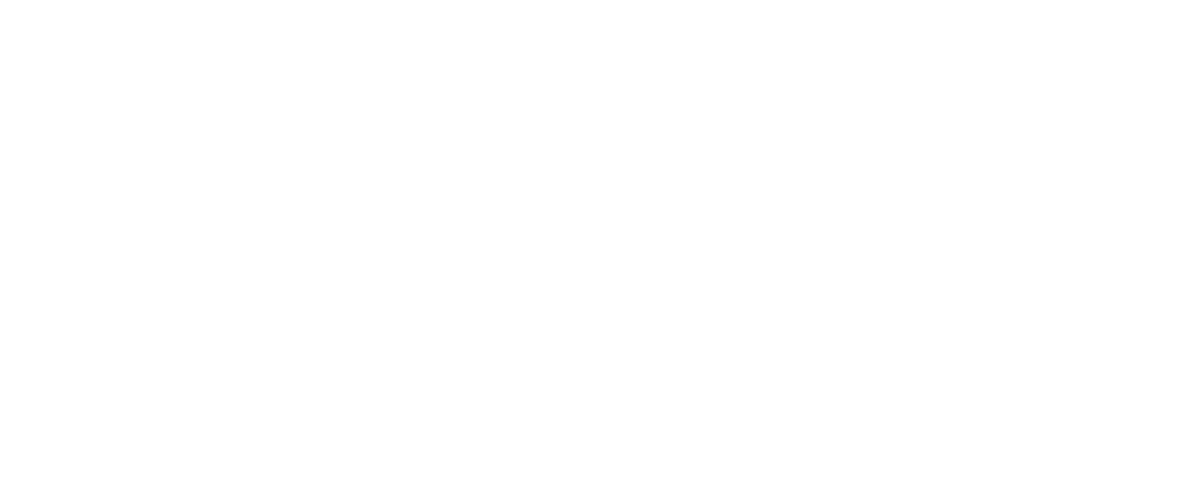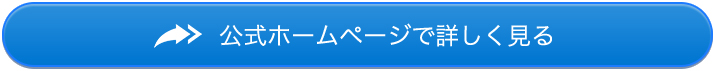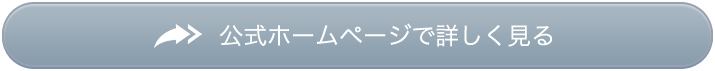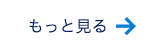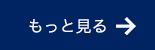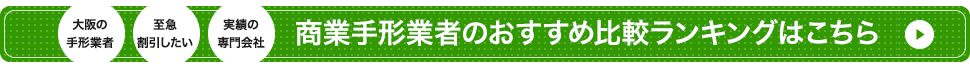滞納などを行った場合の延滞金などの計算方法
特例基準割合というのは毎年、11月30日を経過する時に商業手形の基準割引率に年4%の割合を加算した割合の数値を言い、国税での延滞にかかる税金や利子税、地方税などの延滞金、還付加算金のの算定するのに利用される日本銀行法で定められたものになります。
税金も納期限までに納めないと地方税法の規定によって延滞金が加算されますことや、逆に税金を納め過ぎ出会った場合にも過誤納金と言って、一定の割合で還付加算金をつけて還付を受けることがあります。
こういった延滞金や還付加算金の割合というものは地方税法の特例で、毎年に特例基準割合という規定によって、決定を受けることとなります。
この特例基準割合の率というのは概ね4%程度で推移していて、延滞税では2ヶ月の間での滞納となった場合には年7.3%との小さい方を利率としています。
それ以降延滞した場合には年14.6%と大きく跳ね上がり、1,000円未満の金額出会った場合は切り捨てて、1,000円以上であった場合には100円未満を切り捨てて額を延滞税となります。
特例基準割合の推移というのは?
特例基準割合自体はここ10年ほどに至っては4%程の推移となっていましたが、平成26年からに至っては割合が極端に減り、1.9~1.8%程の従来の半分くらいの割合に推移することとなっております。
この基準割合というものは全国の地方自治体の延滞金に関して、プラス1%を加算して割合を決定していることが殆どで、地方自治体のホームページなどですぐに確認することが出来ます。
こういった数値は非常に見やすくオープンとされていて、税金滞納や還付加算金などに関してお金の動くことになりますので、どの地方自治体でもわかりやすい表や数値の推移を明らかにして公示されています。
こういった滞納などは滞納期限を大きく過ぎなければ良いのですが、実際に長期間滞納した場合には督促状や催告書などが届くことになり、滞納処分となる差し押さえなどされることとなりますので、極力無いようにしたいものです。