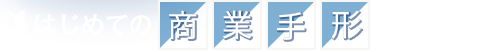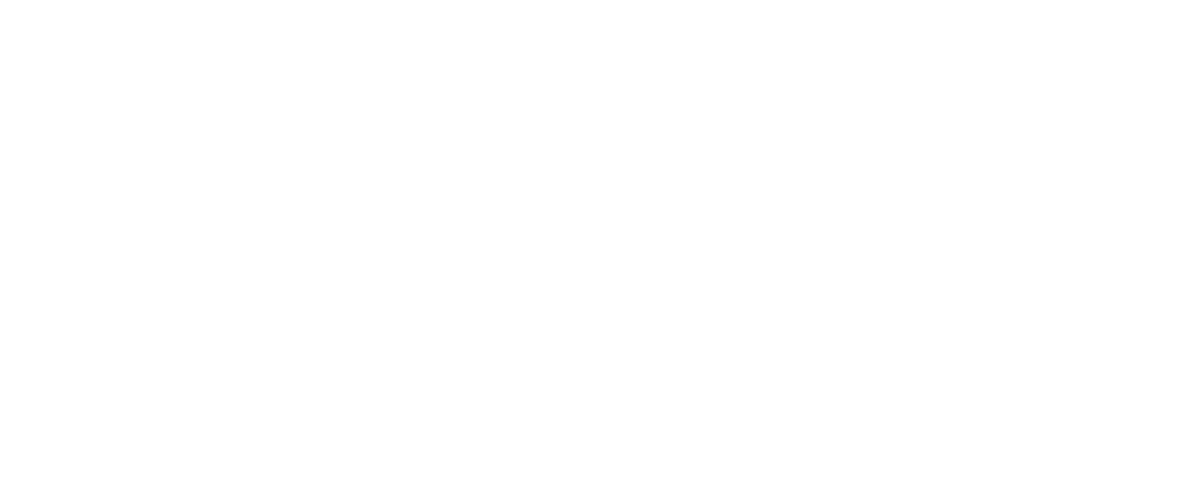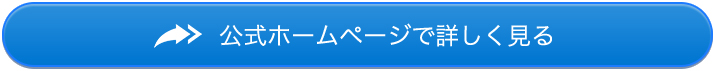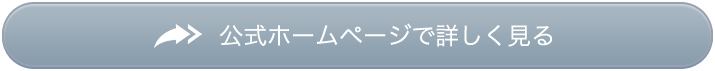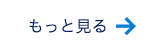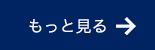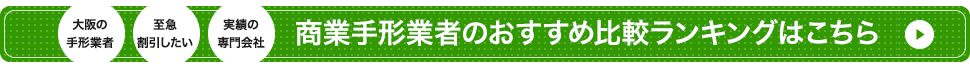何よりも勝る大きな影響の手形
銀行券というのは商業手形と大きく違うのは信用度の違いで、同じような紙のようであっても強制力と影響を与える信用力に大きな違いを持っていると言われています。
商業手形自体は決済が有効とされるまではただの紙とされていますが、この銀行券というのは日本銀行が発行している紙幣なのです。
金本位制下では銀行が振り出す約束手形としての一種で、金などに兌換できていたのですが、現在においては国家の仕切りのもとで完全法貨として強制通用力を持たされた不換紙幣と言われています。
世界の各国での中央銀行で発行される紙幣ということで、日本では日本銀行が中央銀行として日本銀行券として紙幣で使われています。
その発行する枚数や金額というのは日本の長期国債の総額が日本銀行券の流通残高以下に収めるという銀行券ルールという政策目標が定められています。
主に流通しているのは一万円券、五千円券、二千円券、千円券であって、昔では硬貨の材料費が高いために、その材料不足を補うため施策として紙幣の発行を行っていました。
そのため、硬貨と同じようにその額の紙幣を発行していたものでありましたが、今では紙幣に対して硬貨よりも価値を持たせた仕組みの制度となっています。
偽造防止のための技術の粋が集まっている
日本の銀行券の材料では和紙と同じ三椏というものが使用されていて、繊維が丈夫で独特の手触りの感触によって、偽造を防止するものとされています。
よくある紙のパルプ紙での紙幣を製造であった時代には、安易に偽造が横行していたことで、通貨の信用を大きく残ってしまうものでありました。
そうならないように、紙の材質の特性といろいろな施された細工などを用いて、偽造が困難で紙幣の価値を一定に保てるようにその紙の品質を向上させています。
その技術というのは透かしや凹版印刷、マイクロ文字に特殊発光インキなどの様々な施しで、印刷技術も向上させていったのです。
さらにホログラムやパールインク、潜像模様などといったものもここ近年の銀行券の成せる印刷技術の粋を集めたものと世界から絶賛されています。